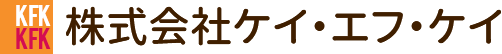米不足から値上がりしたお米。
備蓄米が出回り、徐々に値段が下がってきました。
ただ猛暑などの影響で、今後もどうなるか読めない状況が続いています。
そんな中、お米を止めて麺を増やしている方もいるそうです。
麺類もお米と同様、炭水化物中心の食材。
ただ、調理方法や他の食材の組み合わせが変わるため、栄養バランスには違いが出てきます。
では麺の頻度が上がる時には、どんなことに気を付けていくべきなのでしょうか?
白いご飯と麺類を比べた時、まず思い浮かぶのは塩分の違いでしょう。
スープが多いラーメンやうどん、蕎麦は、それだけ使用する塩分が多くなります。
特に、ラーメンやうどん、そうめんは、スープだけでなく麺そのものにも1食あたり0.7g前後の塩分が含まれており、中でも袋タイプのインスタントラーメンは1食1.0g以上とさらに多めです。
麺そのものの塩分が少ないのは蕎麦。
生麺なら0に近く、茹でた乾麺でも1食分で0.3g程度です。
また、蕎麦に含まれるルチンは血圧を下げる効果もあるため、塩分による血圧への影響は緩和しやすくなります。
少しでも塩分を抑えるには、蕎麦のチョイスがお勧めです。

さらに塩分を減らすためには、余分なスープを身体に入れないことがポイント。
飲み切らずに残すだけでも、スープの塩分を半分以下にカットすることが可能になります。
特にラーメンスープは和麺より量が多い傾向にあり、スープを飲むか残すかで実際に身体に入る塩分の差が大きくなります。
暑い時期にはそうめんやざる蕎麦など、つゆが別添えの冷たい和麺を食べる機会が増えるでしょう。
この時にも、つゆに麺を全て付けて食べるのではなく、下の方だけ付けて食べることで、口に入る塩分を3~4割カットできます。
麺が細いそうめんは調味料が絡みやすく、同じように食べても2倍近く塩分の差が出ることがあります。
迷ったら太めの麺を選ぶことで、塩分は抑えやすくなりますね。
また白いご飯と違い、麺類は単品でも食べやすく、量が多くなってしまいがち。
1食単位で分かれている冷凍麺なら量は明確ですが、乾麺は1人分の量が分かりにくく要注意です。
カロリーで考えると乾麺100gでご飯200g相当なので、表示や測りで確認して茹ですぎないようにしましょう。
ところで、麺類は炭水化物中心の食材なので、単品でバランス良く食べようとすると、トッピングや他のおかずで補う必要があります。
タンメンや五目そば、冷やし中華やサラダ麺などのように、具材をたっぷり乗せた食べ方がお勧めです。

パスタの場合、冷凍パスタをレンジ加熱するか、乾麺を茹でて市販のソースをかけて食べる方も多いでしょう。
冷凍パスタの場合、1食あたりの塩分は2.5~3.0g前後のものが多いですが、乾麺を塩茹でする場合、パスタそのものに含まれる塩分量が増えます。
1.5%の塩水で茹でた時の塩分は、1食あたり麺のみで2.6gとなり、ソースをかけた時には5.0g前後に。
ほぼ全て口に入ってしまうことを思うと、ラーメン以上に注意が必要です。
シンプルな対策としては、茹でる時に加える塩の量を減らすこと。
家庭で食べる分には、お湯2Lに塩小さじ2杯を入れた0.5%濃度で茹でても美味しく食べられます。
コシにこだわらなければ、塩を加えずに茹でるのもアリですね。

他の栄養バランスについては、ラーメンや和麺と同様、具を加えたりサラダを追加したりする必要があります。
市販のソースと一緒に、レンジ加熱したきのこや冷凍野菜を乗せて食べるのは、手軽にできる方法です。
サラダを足す時には塩分が上がり過ぎないよう、ドレッシングは量を控えめにしておきましょう。
もう1点、麺類のネックは魚が登場しにくくなること。
そのため、冷凍パスタは魚介系を選んだり、サラダにスモークサーモンやツナ缶を乗せたり、「魚」を意識して加えることも大切です。
健康管理に大切なn-3系脂肪酸補給のためには、サバやイワシ、サンマなども摂りたいところ。
サラダ麺のトッピングにサバ缶を使うのも良いですね。
ただ刺身や焼き魚、煮魚などは、やっぱりご飯と相性が良い定番メニュー。
これらを週3~4回以上登場させるためにも、ご飯の頻度は減らし過ぎないことをお勧めします。
麺と違って、ご飯は余ったら冷凍できるので、自分に合った量で食べやすいですよ。
米農家を減らさないためにも、私たち消費者が米離れしないことも心がけていきましょう。
手軽にお腹を満たせる麺類。
食べ方に注意して、ほどほどに取り入れて下さいね。
エミ