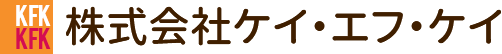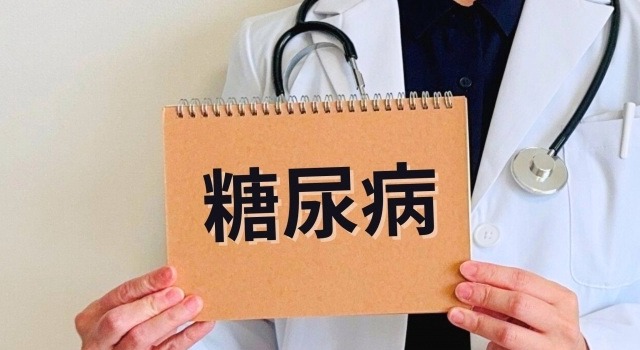
年度も後半に入りましたね。
皆さんは今年の健診を受けましたか?
健診項目の1つである血糖値やHbA1cは、糖尿病の指標になる数値。
一度糖尿病の域に入ると下げるのが難しいので、「ちょっと高め」の段階で食生活を見直すことがお勧めです。
血糖値を下げるポイントの1つは体重管理。
BMI(体重[kg]÷(身長[m]× 身長[m])が25以上の場合は、体重を減らすことから始めましょう。
また、18歳~24歳に肥満だった方や、20歳からの体重増加が大きい方はリスクが高いので、毎年の血糖値の変化を確認し、体重管理を徹底したいですね。
血糖値が高めの場合、2kg落とせば改善効果が期待できると言われています。
もちろん、脂肪を中心に減らすことが大事なので、ペースはゆっくりが基本。
1ヶ月に1kg減を目安にすると良いでしょう。

摂取量を減らすのにやってしまいがちなのが、食事を抜くダイエット。
手軽で効果的に感じるかもしれませんが、とても危険な方法です。
特に朝食を抜くダイエットは、昼の血糖値が上がりやすくなったり、筋肉量を落としやすくしたりしてしまいます。
また、筋肉はエネルギー源として糖質を貯蔵しますが、筋肉が減ると貯蔵庫も少なくなり、血中に糖質が余りやすくなります。
同時に、筋肉が少なくなれば消費エネルギー量も減り、以前より減量しにくい身体になる可能性もあるのです。
安易に1食抜くのではなく、少しずつカットできる部分を探して下さいね。
そのために、まずは食事以外の飲み物や間食の見直しを。
中でも砂糖入りの飲み物は吸収が良く、血糖値を急上昇させますし、カロリーが普通盛りご飯1杯相当の物もあります。
スポーツドリンクも、血糖を上げる点は同様なので、無糖の飲み物に置き換えていきましょう。
間食や食後のデザートでお饅頭やプリンなどのお菓子類を食べていた方は、本当に必要か?改めて考え、量や頻度の見直しをしてみて下さい。

では、ゼロカロリー飲料はどうでしょうか?
飲んだ後に血糖値が上がらない、カロリーがカットできて減量しやすい、という効果があり、短期的には良いかもしれません。
ただ、ゼロカロリー飲料に含まれる甘味料は、摂り続けることにより腸内環境を悪化させ、血糖コントロールにも悪影響を及ぼす可能性があります。
どうしても甘い物が欲しい時に、一時的に利用するのは良いですが、普段はお茶や水での水分補給を心がけたいですね。
ところで、血糖値を上げない糖類に「フラクトオリゴ糖」がありますが、これは善玉菌のエサになって腸内環境も整えてくれます。
甘い飲み物が欲しい時に紅茶やコーヒーに加えて使うのもお勧めです。
但し、使い過ぎは下痢を起こす場合もあるため、適量を守って使うようにしましょう。
シロップや顆粒などで量が異なるため、製品に記載されている適量を参考にして下さいね。
それと、炭水化物はできるだけ控えた方が良いというイメージがあるかもしれません。
しかし、炭水化物エネルギー比は45~65%が推奨されていて、たんぱく質や脂質より多く摂る必要があります。
だからこそ、その質にこだわることは大事です。

そこで注目したいのは主食に含まれるマグネシウム量。
食事から摂るマグネシウムは、糖尿病のリスクを下げると言われています。
例えば玄米ご飯は150gあたり74mgのマグネシウムを含みますが、精米度が高くなるにつれて、マグネシウムの量が少なくなり、5分づきだと半分以下、白米だと7分の1しか残っていません。
また、麺類なら白いうどんより蕎麦が4.5倍、パンなら白いものより全粒粉パンの方が約3倍マグネシウムを多く含みます。
さらに、同じカロリーあたりのマグネシウム量を比較すると、蕎麦や全粒粉パンより、玄米の方が約1.5倍になるのです。
適度に摂りつつ、糖尿病を予防していくためには、玄米が最も優秀な食材と言えますね。

そしてもちろん、運動で消費量を上げる、筋肉を育てることは、血中に糖質を余りにくくしてくれます。
有酸素運動も筋トレも、血糖コントロールの助けになるため、できることから始めてみましょう。
運動する時間が取れない場合は、日常の活動量を上げることも有効です。
通勤時に遠回りしたり、エスカレーターより階段を使ったり、いつもよりちょっと多く動く機会を探して下さいね。
距離によってはバスを使わず歩くのも、身体に良い節約になります。
節約した分つもり貯金をしたり、アプリでポイントが貯まるようにしたり、努力の結果が普段の楽しみに繋がるようにするなど、続きやすい工夫もしておきたいですね。

年齢と共に上がりやすくなる血糖値。
健診で定期的に変化を確認して、今の自分にできることを積み重ねていきましょう。
エミ